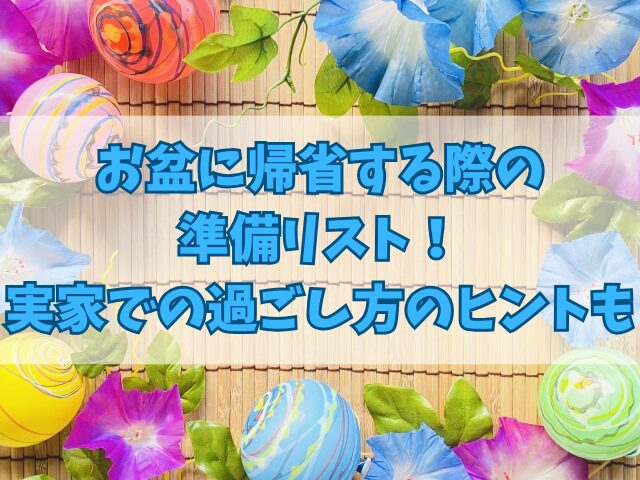お盆休みは、日本人にとって大切な家族の行事のひとつです。
普段なかなか会えない家族や親戚と再会できる貴重な機会でもあります。
本記事では、お盆休みの基本情報から、帰省に役立つ便利グッズ、さらに準備リストや混雑を避けるコツまでを分かりやすくご紹介します。
充実したお盆休みを過ごすためのヒントをぜひチェックしてみてください。
お盆休みの基本|期間と時期を知ろう
お盆とは?お盆休みの意味を解説
お盆とは、先祖の霊を迎えて供養する日本の伝統的な行事です。
一般的には8月13日から16日までの4日間を指します。
この期間中、家庭では仏壇にお供え物をしたり、迎え火・送り火を焚いたりします。
また、お墓参りをする家庭も多く、家族が一堂に集まって過ごす時間は心を整えるひとときでもあります。
日本全国で共通の慣習ではあるものの、地域によって風習や細かな儀式は異なります。
お盆休みはいつから?日程を確認
お盆は、8月13日から8月16日までの4日間です。
この期間が公的な休暇として設定されているわけではありませんが、多くの企業や公共機関がこの時期に合わせて休業となります。
さらに、前後の土日や有給休暇を組み合わせて、8月10日〜17日といった長期休暇を取る方も少なくありません。
そのため、交通機関の混雑や宿泊施設の予約も早めの対応が重要です。
地域によるお盆の期間の違い
全国的には8月のお盆が主流ですが、東京をはじめとする一部の地域では7月15日を中心とした「新盆(しんぼん)」の文化が根付いています。
また、沖縄や奄美などでは旧暦に合わせた「旧盆」が行われるなど、地域によってお盆の期間や風習に差があります。
そのため、帰省先や訪問先の習慣を事前に確認しておくと、よりスムーズで心地よい交流ができるでしょう。
お盆に帰省する際の準備リスト

帰省前にチェックしておきたい準備
- 自宅の戸締りと火の元の確認は、外出前日の夜に再確認するのがおすすめです。特にガスの元栓やブレーカー、窓の施錠などは見落としがちなので注意しましょう。
- ペットや植物の預け先の確保は、できれば1週間以上前に手配しておきたいところ。ペットホテルや信頼できる知人へのお願い、観葉植物には自動給水器なども便利です。
- 郵便物の一時停止や宅配の手配も忘れずに。日本郵便の「不在届サービス」や宅配ボックスの設置で、防犯対策にもつながります。
必要な物品と便利グッズ
- モバイルバッテリーや充電ケーブルは家族全員分あると安心。車用充電器やモバイルWi-Fiルーターも活躍します。
- 帰省中の手土産(地元のお菓子や特産品)は、相手の好みに合わせて選ぶと喜ばれます。冷蔵が必要な場合は保冷バッグも用意しましょう。
- マスク・除菌グッズ・予備の薬類に加え、常備薬や虫刺され対策、熱中症対策グッズ(冷却シート・塩分補給飴)も入れておくと安心です。
- 子供向けの暇つぶしアイテム(タブレット・絵本など)は、音が出るものはイヤホンを忘れずに。お絵描き帳やパズルブックもおすすめ。
時間を有効に使うための計画
渋滞や混雑を避けるには、出発時間の工夫がカギです。
早朝や深夜に出発する、平日を避けて移動するなどの方法がおすすめです。
また、ナビアプリで渋滞予測を確認しておく、サービスエリアの休憩ポイントを事前に決めておくなど、時間のロスを減らす工夫も有効です。
実家での過ごし方:快適にするための工夫
- Wi-Fi環境を確認しておくと、仕事や子どもの学習にも便利。必要であればポケットWi-Fiを持参するのもおすすめです。
- 休息時間をしっかりとるためには、自分のスケジュールも大切に。昼寝用のアイマスクや耳栓があるとリラックスしやすくなります。
- 食事の分担や家事の協力体制を相談しておくと、実家でも過ごしやすくなります。特に長期滞在の場合は、炊事・洗濯などを一緒に行うことで双方のストレスが減ります。
お盆休みのイベントとアクティビティ
地域別の人気イベントをチェック
各地で開催される盆踊りや花火大会、灯籠流しなどはお盆ならではの風物詩です。
特に京都の「五山の送り火」や長岡の花火大会、青森ねぶた祭などは全国的にも有名で、多くの観光客が訪れます。
地方によっては地元住民が参加する町内盆踊りや縁日、提灯を灯す伝統行事なども開催され、地元の文化を肌で感じることができます。
これらのイベントは観光協会の公式サイトやSNSなどで詳細が発信されることが多いため、事前の情報収集が大切です。
夏季休暇を満喫する遊び場情報
- アスレチックや公園など家族向けの施設:自然の中で思いっきり体を動かせるアクティビティは、子どもたちにも大人気。最近ではキャンプ場併設の施設や、バーベキュー場付きのパークも人気です。
- 海や川でのレジャー(安全対策を忘れずに):ライフジャケットの着用や熱中症対策、水遊び用のシューズなど、安全を考えた準備が必須です。釣り体験ができる施設も家族連れに人気です。
- 涼を感じる高原や避暑地:長野・軽井沢・那須高原などは、標高が高く気温も比較的低め。自然の中で過ごすことでリフレッシュにもつながります。滝や渓谷などの観光地を巡るのもおすすめです。
プールや温泉のおすすめスポット
- 温泉旅館でゆったり過ごす:客室露天風呂付きの宿や、子ども向けの浴場が用意されている施設も多く、家族全員が楽しめます。
- 屋内・屋外のレジャープール:流れるプールや波の出るプールがある大型施設では、一日中遊び尽くせます。夜間営業しているナイトプールも人気。
- 家族風呂のある施設も人気:プライベート空間で安心して入浴でき、小さな子ども連れにも好評です。中には岩盤浴やキッズルームを併設している施設もあります。
帰省前の最終チェックリスト

必要書類と持ち物の確認
- 健康保険証・運転免許証などの身分証明書:急な病気や事故に備えて、コピーも用意しておくと安心です。
- 現金や交通系ICカード:地方では現金しか使えない店もあるため、多めに準備しておくのがおすすめ。ICカードはチャージを事前に済ませておきましょう。
- 宿泊予約の確認書類やアプリ:印刷した紙媒体に加えて、スマートフォン内のアプリでも確認できるようにしておくと便利です。併せてキャンセルポリシーの確認も忘れずに。
- 忘れがちな小物類:充電器やイヤホン、老眼鏡、常備薬、筆記用具なども事前に用意しておきましょう。
交通手段の選択と予約方法
- 新幹線や飛行機の予約は早めに:繁忙期はすぐに満席になるため、1ヶ月前からの予約が理想的。指定席やグリーン車の検討も。
- 高速バスやカーシェアも選択肢に:リーズナブルに移動したい方には高速バスが便利。カーシェアは乗り捨て可能なプランもあり、柔軟な移動に対応できます。
- 車移動の場合は、事前にメンテナンスを:タイヤの空気圧やオイル交換、バッテリーのチェックを出発前に済ませておくと安心です。ドライブレコーダーの動作確認もおすすめ。
- 渋滞対策グッズも準備:首用クッション、携帯トイレ、車内用スリッパ、飲料水などがあると快適です。
混雑を避けるための移動計画
- 渋滞情報をリアルタイムでチェック:NEXCOの渋滞情報サイトやTwitter公式アカウントを活用すると、タイムリーな情報が得られます。
- Googleマップやナビアプリを活用:出発前に目的地までのルートを複数確認しておくと、急なトラブルにも対応しやすくなります。
- 早朝・夜間移動を検討:深夜出発や朝5時台の出発は、比較的道路が空いており、気温も低めで快適。休憩スポットの営業時間も事前に確認しておきましょう。
お盆に関するお役立ち情報
お盆関連のキャンペーン情報
ショッピングサイトや旅行サイトでは、お盆限定の割引キャンペーンや特別プランが多数あります。
たとえば、楽天トラベルでは地域限定クーポンや早期予約割引、じゃらんでは「家族旅行応援プラン」や「お盆直前セール」など、家族旅行や帰省に合わせたお得なサービスが提供されています。
さらに、AmazonやYahoo!ショッピングでもお中元ギフトの割引や、アウトドア用品、移動グッズなどのお盆特集が組まれていることが多く、時期を逃さずにチェックするのがポイントです。
アプリの通知設定をONにしておくと、タイムセール情報を逃さずにすみます。
お盆の費用を抑える方法
- 帰省費用は早割やLCCを活用:特にLCCは座席数が限られているため、早めの予約が肝心です。また、乗車・搭乗日の変更がしやすいプランもあるので、万一の予定変更にも柔軟に対応できます。
- 手土産は地元のスーパーやネット購入で安く抑える:最近では地元名産品を扱うネットショップでも送料無料キャンペーンが実施されていることがあり、お得に入手可能です。
- 宿泊先の家族割引や連泊プランを利用:ホテルによっては、子ども添い寝無料や連泊時の食事割引などが付くケースもあります。公式サイトからの予約でしか適用されない特典もあるため、複数のサイトを比較するのが賢明です。
家族や友達との連絡方法の工夫
- グループLINEで予定を共有:スケジュール表やチェックリストを画像で送ると、視覚的に把握しやすくなります。リマインダー機能を活用するのも便利です。
- 帰省スケジュールをカレンダーアプリで一括管理:GoogleカレンダーやTimeTreeなど、共有可能なカレンダーアプリを使えば家族間での情報共有がスムーズになります。
- 写真や動画をリアルタイムで共有すると話題も広がります:Instagramの非公開アカウントを作って家族内だけでシェアする、またはGoogleフォトのアルバム共有機能を使うと、思い出の記録がより簡単になります。
まとめ
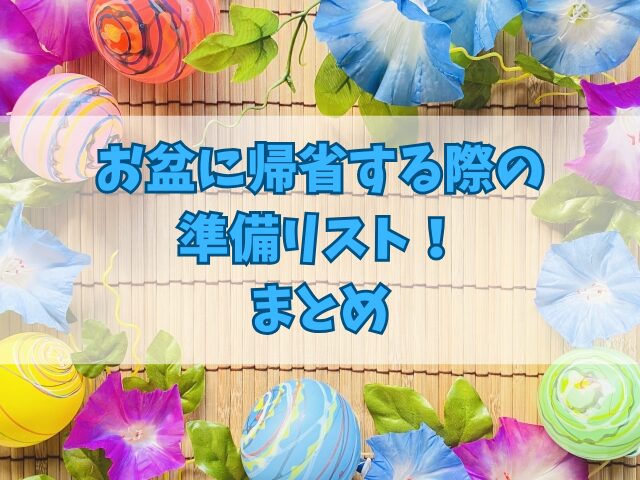
お盆休みは、大切な人と再会し絆を深めるチャンスです。
しっかりと準備をしておけば、ストレスなく楽しい時間を過ごすことができます。
便利グッズや準備リストを活用して、2025年のお盆をより有意義なものにしてください。